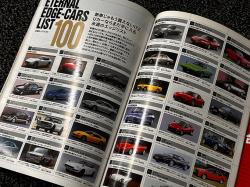【スーパーカーにまつわる不思議を考える】 “未来”を見つめ続けるランボルギーニが送り出した「新型PHEVスーパースポーツ」の新たなる価値とは?
カテゴリー: トレンド
タグ: ランボルギーニ / 4WD / EDGEが効いている / 越湖信一
2024/09/20
 ▲2024年のモントレー カーウイークでお披露目されたPHEVスーパースポーツ「テメラリオ」。ウラカンの後継モデルとなる
▲2024年のモントレー カーウイークでお披露目されたPHEVスーパースポーツ「テメラリオ」。ウラカンの後継モデルとなるスーパーカーという特殊なカテゴリーはビジネスモデルとして非常に面白く、それ故に車好きにとって興味深いエピソードが生まれやすい。しかし、あまりにも価格がスーパーなため、多くの人はそのビジネスのほんの一端しか知ることができない。今回は新型PHEVスーパースポーツから、“未来”を見つめるというランボルギーニのブランドDNAを探ってみたい。
理想形に限りなく近づいた“フォリクラッセ”なスーパースポーツ
「ランボルギーニには歴史がない。だから目指すところは最初から“未来”だった」とは、ランボルギーニのチーフエンジニアでありながらCEOとしてカウンタックやウラッコを生み出したパオロ・スタンツァーニの言葉だ。
長い歴史や、レースのヘリテージをもつ同じモデナ地区のライバルであるマセラティやフェラーリと比べて1963年に誕生した新興ブランドには過去のよりどころは何もなかった。その中で、ひたすら未来を見つめるというランボルギーニのブランドDNAを設定したスタンツァーニの判断は正しかった。そしてそれは今のランボルギーニにも生きている。
カウンタックというレースカーでもなければGTカーでもない、カテゴリーを超えた存在はまさに“スーパーカー”であった。フラッグシップとしてのカウンタックに加えて、パフォーマンスと実用性を両立したインテリジェントなスポーツカーとして誕生したのがウラッコだ。そして、そのコンセプトは、今回モントレーカーウイークにてデビューを飾ったテメラリオにも正しく受け継がれていると感じる。
ランボルギーニはフラッグシップV12を熟練したクラフトマンシップによって、聖地であるサンタアガタでゼロから作り上げるということにこだわった。それは現在のレヴエルトに継承されている。時代をさかのぼって、1970年代にボディを含め内製化にこだわったのはモデナ地区ではランボルギーニだけであった。これはフェルッチオ・ランボルギーニの工業製品として世界に認められるためにはビス1本からこだわらねばならない、というポリシーにも基づいている。
一方、ウラッコをその起源とするガヤルド~ウラカンは、多くのランボルギーニを愛するファンに向けて門戸を開くモデルとしての使命をもって生まれた。特にウラカンは大きなセールスを記録した。フォルクスワーゲン グループのリソースを効率的に活用し、生産性も高かったから、顧客の需要に対してタイムリーに応えることができたのだ。
 ▲内外装のデザインは“ヘリテージを生かしつつミッドエンジンスポーツカーの未来への方向性を示すスタイル”と紹介された
▲内外装のデザインは“ヘリテージを生かしつつミッドエンジンスポーツカーの未来への方向性を示すスタイル”と紹介された ▲フロントアクスルに2基のモーターを配したe-4WDを採用。0→100km/h加速は2.7秒となる
▲フロントアクスルに2基のモーターを配したe-4WDを採用。0→100km/h加速は2.7秒となるさて、ブランニューのテメラリオだが、ランボルギーニ スポーツカーとして求められる理想形に限りなく近づけた力作であると筆者は考える。そう、このモデルの革新性をランボルギーニのCEO、ステファン・ヴィンケルマンは「フォリクラッセ(Fuori Classe)」、つまり、クラスを超えたユニークな存在と表現した。つまりかつての“ベビーランボ”という立ち位置から完全に突出し、新しいバリューを提案するモデルに仕上がっているということだ。
何よりボディのプロポーションが美しく、細部の処理もきわめてエレガントだ。空力や放熱の問題をクリアしつつも、クリーンなディテイル処理を追求したのは、デザイントップであるミティア・ボルケルトの力量だ。テメラリオはウラカンと比較して、かなりキャビンサイズが大きくなっている。ミティアいわく「これから10年は主力モデルとして活躍してもらわなければならないから、あらゆるディテールをゼロから見直した」ということだが、ルーフまでの室内高は34mm余裕ができたというし、シート後方のラゲージスペース、拡大されたフロントのコンパートメントなど、実用性を高めている。
ウラカンのサイドウインドウの強い傾斜をもつタンブルホームのボディ形状が、テメラリオでは緩やかになっている点が顕著だ。これによってキャビン内の開放感は大いに高まっているが、シャープなスポーツカーとしてのテンションも弱まることはない。
実際、テメラリオはウラカンより180mmほど全長は長いが、レヴエルト比では273mm短く、クラスの違いをはっきりと表現している。ボディがウラカンより一回り大きくなっているが、キャビン、そして車両自体をコンパクトに見せるための試みが各所に見られる。リアのトンネルバック形状もそれに寄与している。
電気モーターと組み合わされたL411と称される新しいツインターボエンジンもまた“フォリクラッセ”だ。これだけの高回転型でハイパフォーマンスのパワートレインの採用は、これまでのV10エンジンの存在を振り返らせることのない新たな説得力をもつ。高回転自然吸気エンジンと同様のレスポンスを提供するというこのエンジンは180度のフラットプレーン型クランクシャフトを備え、ドライサンプ仕様である。シャシーも新たに開発されたアルミ押し出し材をベースとしたスペースフレームが採用され、さらなる高剛性を追求するとともに、生産性も考慮されている。
 ▲デザイン部門(チェントロ・スティーレ)の統括責任者、ミティア・ボルケルト
▲デザイン部門(チェントロ・スティーレ)の統括責任者、ミティア・ボルケルト ▲ミティア・ボルケルトが記した、テメラリオにおける“デザイン DNA”のポイント
▲ミティア・ボルケルトが記した、テメラリオにおける“デザイン DNA”のポイントテメラリオの登場で、ランボルギーニとしての脱炭素化追求ロードマップ“コル・タウリ”におけるハイブリッド化への移行が完了した。次なる試みは、BEVモデル「ランザドール」のリリースとなる。
“未来”をブランドのDNAとするランボルギーニにとって今回のテメラリオのリリースは、究極の内燃機関エンジンの追求という点でブランドのファンにとってはたいへんわかりやすいものであり、市場での高い評価を得るのではないだろうか。スタイリング面においてはレヴエルトのモチーフを生かしつつも、より広いターゲット層へアピールするハイクオリティな仕上がりをアピールできている。このなかなかエレガントな造形を眺めた筆者は、ランボルギーニGTの原点である350GTのエレガントな佇まいを連想したのであった。
 ▲ランボルギーニのチェアマン&CEOであるステファン・ヴィンケルマン
▲ランボルギーニのチェアマン&CEOであるステファン・ヴィンケルマン ▲800psの4L V8ツインターボエンジンに3基のモーターを組み合わせ、システム最高出力920psを発揮する
▲800psの4L V8ツインターボエンジンに3基のモーターを組み合わせ、システム最高出力920psを発揮する ▲“ベビーランボ”の元祖となる「ウラッコ」。V8エンジンを横置きでリアミッドにレイアウトした
▲“ベビーランボ”の元祖となる「ウラッコ」。V8エンジンを横置きでリアミッドにレイアウトした ▲2023年のモントレー カーウィークで発表されたBEVのコンセプトモデル「ランザドール」
▲2023年のモントレー カーウィークで発表されたBEVのコンセプトモデル「ランザドール」
自動車ジャーナリスト
越湖信一
年間の大半をイタリアで過ごす自動車ジャーナリスト。モデナ、トリノの多くの自動車関係者と深いつながりを持つ。マセラティ・クラブ・オブ・ジャパンの代表を務め、現在は会長職に。著書に「フェラーリ・ランボルギーニ・マセラティ 伝説を生み出すブランディング」「Maserati Complete Guide Ⅱ」などがある。
【関連リンク】
日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
あわせて読みたい
 【徹底考察】ランドクルーザーFJとジムニーノマド、どっちがいいの? 両モデルの特徴や違い、買うべき人を本気で考えてみた!
【徹底考察】ランドクルーザーFJとジムニーノマド、どっちがいいの? 両モデルの特徴や違い、買うべき人を本気で考えてみた! ’94 スズキ カプチーノ|スズキ渾身のマニアックなオープン軽スポーツ【名車への道】
’94 スズキ カプチーノ|スズキ渾身のマニアックなオープン軽スポーツ【名車への道】 リフトアップされた“武闘派”のランクル80は、幼少期から刷り込まれた父との思い出の結晶
リフトアップされた“武闘派”のランクル80は、幼少期から刷り込まれた父との思い出の結晶 運転ビギナーは気づいていない!? ボルボの安全研究・開発担当エキスパートが30年間の蓄積データで語る安全運転のコツ!
運転ビギナーは気づいていない!? ボルボの安全研究・開発担当エキスパートが30年間の蓄積データで語る安全運転のコツ! 空冷ポルシェ 911こそ、いま選ぶべき「最後のアナログ・スポーツカー」だ!【カーセンサーEDGE 2026年2月号】
空冷ポルシェ 911こそ、いま選ぶべき「最後のアナログ・スポーツカー」だ!【カーセンサーEDGE 2026年2月号】 【爆増】ランクル250の流通台数が1000台突破! 価格も検討しやすくなってきた最新型ランドクルーザーの中古車状況、オススメの狙い方を解説
【爆増】ランクル250の流通台数が1000台突破! 価格も検討しやすくなってきた最新型ランドクルーザーの中古車状況、オススメの狙い方を解説 スーパーカー界の2025年を振り返る。何が起こるかわからないエキサイティングな年だった!【スーパーカーにまつわる不思議を考える】
スーパーカー界の2025年を振り返る。何が起こるかわからないエキサイティングな年だった!【スーパーカーにまつわる不思議を考える】 新車だと800万円超えのラングラーが300万円から狙えるが買いなのか? ジープ伝統のSUVのモデル概要、オススメの狙い方解説!
新車だと800万円超えのラングラーが300万円から狙えるが買いなのか? ジープ伝統のSUVのモデル概要、オススメの狙い方解説!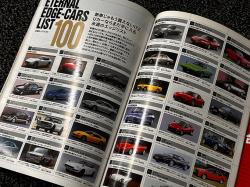 あの時買っときゃ良かった……のモデルを振り返り“後悔を楽しむ”「バブルが生んだ国産オープンモデル」編
あの時買っときゃ良かった……のモデルを振り返り“後悔を楽しむ”「バブルが生んだ国産オープンモデル」編 「ネオクラ・メルセデス」がアツい! 正規ディーラーも参入するほど中古車市場でいま静かに熱を帯びているR129型、W124型に注目!
「ネオクラ・メルセデス」がアツい! 正規ディーラーも参入するほど中古車市場でいま静かに熱を帯びているR129型、W124型に注目!

 Xをフォロー
Xをフォロー